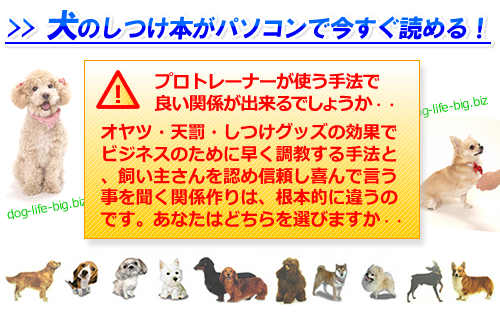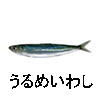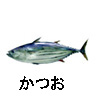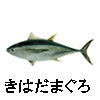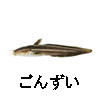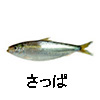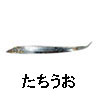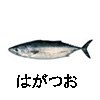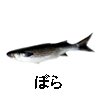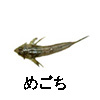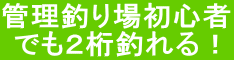| いさき |
|---|

 |
生態:沖合いの岩礁域や貝殻混じりの砂泥域に生息する。
浅海の黒潮流域沿岸部の岩礁域にも群れて生息する。
大型では50cm近くまで成長する。
側線のすぐ下から背中にかけて茶色の縦ジマが3本ある。中・小型はとくに縞が鮮明だが、大型になると目立たなくなる。
初夏に産卵のため岸近くにやってくる。産卵を控えたイサキは大群で押し寄せ、根の中層を占拠するが、その場所は毎年決まっているという。
卵は1mm弱の浮性卵で、数は雌の大きさによって6万から105万粒と大きく違う。
釣り方:中層に密な魚群を形成するため、船からサビキ、カラバリ、コマセ釣りなどで釣るのが一般的だが、接岸中は磯からも釣れる。
群れで行動し、コマセによく集まる。
このためイサキ釣りはコマセの使い方が重要とされる。
沖釣りではシャベルカゴ、ビシを使った釣りで、コマセ、付けエサはオキアミを使う。
小型が多い群れではウイリーやスキンのバケもいい。
磯釣りはカゴ釣りが主流で、反転カゴにオキアミをエサにする。大型を釣るなら磯の夜釣りがいい。
食べ方:イサキは塩焼きが定番で美味しいが、他に刺身、アライ、なめろう、つけ焼きなどが美味しく、小さいものでも脂が乗っているので寿司ネタなどに利用される事もある。
イサキの背鰭の棘は、鶏のトサカに似ているので、「鶏魚」 とも書く事がある。この棘は堅く、紀州ではイサキのことを 「カジヤゴロシ」 というほどで、塩焼きで食べる時は十分注意する必要がある。
喉に刺さるとまず激しく痛み、場合によっては病院行きになる場合がある。
|
脳を鍛える!算数問題をご案内 | 関東の海で釣れる魚をご案内 | 写真屋sarutaのご案内 | 心躍る絵本をご案内 |
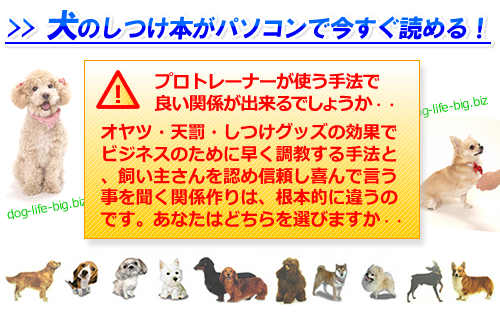
|